各地で大雨が降りました。大雨や土砂災害が心配な時期ですが、この後は台風シーズンも控えています。そうなると気になるのが、多くの人が集まる避難所。きょうは、コロナの収束が見えない中での避難所は、どんな危険性があるのか?どう防げばいいのか?7月2日TBSラジオ「森本毅郎・スタンバイ!」(月~金、6:30~8:30)の「現場にアタック」で、レポーター田中ひとみが取材報告しました。
まずは、今年5月いち早く「事前の備え」を呼びかけた、防災学術連携体の代表幹事・米田雅子さんに伺いました。
★コロナ+災害でダブルのリスク
- 防災学術連携体・代表幹事 米田雅子さん
- 「大変雨の多い時期なので、このような時に災害が起きて避難所に行ったら、避難所が3密になってしまって、今度は新型コロナウイルスに避難所で感染してしまうという「ダブルのリスク」に襲われる危険性がある。一人一人が距離を取る、ダンボールで仕切るなど、間隔を空けておかなければならない。また、自然災害はインフラがよく止まる。特に水道と電気が止まると衛生状況が悪くなったり、手が洗えなくなったりするので、普通よりももっと厳しい衛生環境になる。そこで「分散避難」と呼んでいるが、それぞれの方が避難できる場所を、自分で探しておくことが大事だと思う。」
避難所はまさに3密(密閉・密集・密接)。多くの自治体は、避難所での1人当たりのスペースを、畳1畳より一回り広い「およそ2平方メートル」確保しているそうですが、そこに布団や生活必需品を持ち込んだりするので、寝返りを打つと隣と体がぶつかってしまうこともあるような小さなスペースです。
そこで、人と間隔を開けたり、段ボールで仕切りを作ったり、体育館の他に教室にも避難場所を拡張したり、早急に避難所の運営方法を見直す必要があると言うことでした。
また、キーワードで挙げていたのは「分散避難」。自治体は避難所を増やす、個人は避難所だけを利用せず、知り合いや親戚の元を頼るという「分散避難」も考えて欲しいと仰っていました。
★3.11で起きたインフルエンザの集団感染、どう対応した?
ただ、現実に避難所で集団感染が起きた場合、どう対処すればいいのか。実際に東日本大震災で起きた、ある避難所の集団感染について、当時現場で対応に当たった方に話を聞くことができました。東北医科薬科大学・教授の遠藤史郎さんのお話。
- 東北医科薬科大学・教授 遠藤史郎さん
- 「仙台市の隣にある名取市の避難所を巡回していた医師会の先生方から連絡があって、避難所の中でインフルエンザが集団発生している、なかなか発生数が収まらない、手伝いに来てくれないかという連絡があった。症状のある方には検査をして確認されれば隔離するという流れで診療を行っていたが、その中でどんどん増えている状況だったので、何か抜けがないかということを確認していった。当時、避難所には手を洗うためのアルコール製剤が供給されるようになっていた時期だったが、使用量がかなり少なかった。あとは当時外気温が低かったので換気をするのが難しい。また、マスクの着用率が大分少なく見えたので、その3点を強化して、インフルエンザの集団発生を抑制していった。」
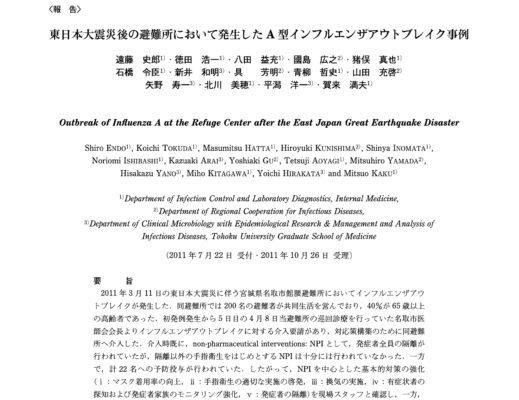
遠藤史郎さんたちの論文
当時、現場で動いていた医師会から、どうにも感染者数が収まらないと、遠藤さんが所属していた東北大学病院のチームに、助けを求められたそうです。この時は、小学校の体育館に避難していた約200人の被災者のうち、20人がインフルエンザを発症。
遠藤さんたちは現場を観察して、手洗いなど基本的な部分の見直しや、疑わしい人にはその場で検査を行った他、感染者を体育館から教室に隔離する「分散避難」をして、爆発的な感染拡大を防いだそうです。
冒頭の米田さんも「分散避難」のために、体育館だけでなく、教室も開放して欲しいと訴えていました。
★コロナ禍の避難所、キーワードは「分散避難」
いずれにしてもやはり、避難先をいかに増やして分散させていくか、ということが課題になりそうです。では都内では現状どうなっているのか。足立区で、23区で初めてという分散避難の取り組みが始まったというので、災害対策課長、会田康之さんに聞きました。
- 足立区・災害対策課長 会田康之さん
- 「都営住宅が足立区は多いんですが、そこにお住まいの方が、上層階に空いてる部屋があるので開けて欲しいという要望をいただき、東京都にお願いをして協議を重ね、今年度から11団地・16戸の空き住戸を活用できるようになった。都内では初の取り組みで、足立区が第一号として東京都と協定結んで、今シーズンから使えるようになっている。どうしても都内は場所がなく、人数も多いので、あるものを利用するというのが今の考えです。」
これは水害リスクのある低層階に住む人に、上の階の空き部屋を利用してもらう取り組みで、都内初。都営住宅16部屋に加え、区営住宅19部屋ということで、ようやく一歩踏み出した程度ですが、足立区では、このほかに、民間施設・警察署と協力して160施設を、分散避難ように確保したそうです。
最初の米田さんも言っていましたが、台風などの水害では、避難=体育館などの避難所だけではなく、自宅の上の階への住宅避難、ハザードマップで安全な知人宅への縁故避難、そして、今回の都営住宅などの上の階の空室を利用する垂直避難など分散避難の選択肢を増やすことが重要だそうです。
また、ここで気になったのが、東京都が借り上げていた感染者隔離用のホテル。ここも活用できるのではと思って都に話を聞いたところ、元々5軒あった内、現在2軒に稼働が減っているということ。コストを考えると借り続けるのも困難で、神奈川県は8月以降はホテルの「借り上げはやめるということでした。感染症対策と避難所をどう両立させていくか、喫緊の課題です。

田中ひとみが「現場にアタック」でリポートしました!



