新型コロナウイルスの緊急事態宣言中に「献血の協力者数が大幅に減少した」という報道があり、このままだと安定的な供給に影響を及ぼしかねないという話が出ていました。その後、5月25日に緊急事態宣言は全面解除されて、街の中の人出が増えてきましたが、では、献血はどうなったのか?
6月25日TBSラジオ「森本毅郎・スタンバイ!」(月~金、6:30~8:30)の「現場にアタック」で、レポーター田中ひとみが取材報告しました。
まずは東京都赤十字血液センター・推進係の、大川由紀子さんのお話。
★献血バスの運行が大幅減少!宣言解除後も7割の稼働に留まる
- 東京都赤十字血液センター・推進係 大川由紀子さん
- 「「献血ルーム」については土日に外出する人が増えてきたので、土日を中心に、目標とする協力人数に到達、回復してきている。ただ「献血バス」については、今現在も目標数値に対して7割程度のご協力。やはりお伺いしている先が企業や大学などの教育機関なんですが、在宅勤務を推奨していて協力者の見込みが立たず延期を判断したり、大学においても、今はオンライン授業を進めているので、キャンパス内に人がいない状況で献血バスを出す状況にない。今までに例を見ない状況。企業や団体の関係者が聞いていたら、是非、献血の実施をご検討いただけると助かります。」

東京都赤十字血液センター ホームページ
元々目標数値を多めに見積もっている為、切迫した状況ではないということですが、「まだ緊急事態宣言前の状況には戻っていない」ということでした。赤血球や血小板は、長期保存ができないので、常に確保し続ける必要があるので心配です。
そもそも献血ができる場所というのは、常設の「献血ルーム」と、企業、学校、イベント会場などに出張する派遣型の「献血バス」があります。今回、特に影響が大きかったのが献血バスの方で、都内では2〜6月にかけて、5割のバスの運行を中止。実に700回以上のバスの稼働が中止や延期に。
ちなみに、献血は「不要不急には当たらない」必要なものなので、緊急事態宣言中も駅前などで活動していましたが、やはり企業などの団体組織への派遣がないと、量は大きく増えません。緊急事態宣言が解除されても、この団体派遣が回復しないので、引き続き、協力を求めていました。
献血会場においては、様々な感染症防止の対策を行っており、安心して献血いただける環境を整えております。また、混雑回避のためにも、事前のご予約をお願いしております。
献血でいただく血液は、輸血を受ける患者さんを救うことができる唯一の手段です。患者さんが安心して治療に専念できますように、引き続き献血へのご協力をお願いいたします。
特に、少し先の話になりますが、これから迎える秋から冬の時期は例年献血協力者が減少してしまう時期が迫ってまいります。企業・団体・町会等の関係者の方がいらっしゃいましたら、是非現状をご理解いただき、今後の献血実施をご検討いただけますと大変ありがたく存じます。
★4月・5月のドナー登録者数は1000人を割り込む
そしてもう一つ、命に関わる骨髄バンクのドナー登録はどうなったのか?こちらも取材しました。公益財団法人・日本骨髄バンクの小島 勝さんのお話。
- 公益財団法人・日本骨髄バンク 小島 勝さん
- 「4月・5月の新規のドナー登録者は、大変残念ながら減ってしまいました。4月が873人、5月が781人の新規の登録者数だった。昨年の4月は5322人、5月は4737人の新規の登録者があった。ただ、緊急事態宣言明けた後、徐々に新規の登録者は復活しつつあるかと思いますので、一時的な数字かなと思っております。」
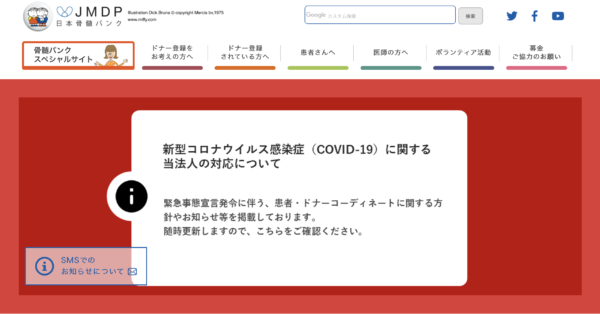
日本骨髄バンク ホームページ
去年は、競泳選手の池江璃花子さんが白血病を公表した影響もあって、特に登録者数が増えましたが、例年でも、4月、5月はそれぞれ2000人ほどの新規の登録があったということなので、やはり今年は数としては大きく減っているようです。
どうしてこんなに減ってしまったのかというと、ドナー登録ができる場所は、献血ルームが3割、献血バスが7割ということで、ドナー登録は献血と一緒に呼びかけているそうなんです。ですので献血バスの稼働が大きく減ったことが、ドナー登録の数も大きく左右していたようです。
★提供に結びつける環境整備も大事
ただ、去年だけで2年分の登録があったそうなので、ドナー登録はしばらくは安心かなと思ったんですが、小島さんは、数が多ければ良いという話でもないと仰っていました。
- 公益財団法人・日本骨髄バンク 小島 勝さん
- 「ドナー登録は、55歳の誕生日を迎えると取り消しになる。いま40、50代が半数以上を占めている。ということは、ここ10数年で卒業するドナーばかり。なので、10〜30代の若い方の登録が課題。また、登録した後のドナーさんが提供できる環境作りも重要。と言うのも、患者と白血球の型が一致すると適合通知がドナーに行き、その時点から提供に向けたコーディネートが始まるんですが、ドナーのご都合でお断りされるケースも多い。仕事が忙しい、会社の理解が得られない、子育て中、介護など。やはりこういったところも解決していかなくてはならない、重要な課題として捉えている。」
ドナーは提供者の健康状態の影響もあるので、年齢が54歳までと制限されています。そのため、毎年多くの方がドナーを卒業するので、常に若い方の登録を増やさなければいけません。
また骨髄移植の際、せっかく白血球の型が一致しても、実際に骨髄の提供に至るのは、約5%に留まるそうなんです。勿論、年齢の問題や健康上の理由もありますが、提供するのに10日前後の休みが必要なので、それが取れないと断念するケースが非常に多い。
小島さんたちは、「ドナー休暇制度」の導入を企業に働きかけたり、自治体に資金的な援助を求めたりして「登録者数」だけでなく、「提供に至る割合」を何とか引き上げたいと仰っていました。

田中ひとみが「現場にアタック」でリポートしました!



